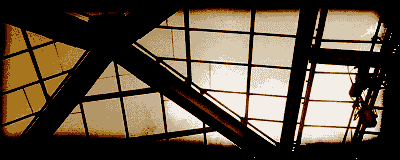
ただ一人の乗客を降ろしたバスが、ガリガリと砂埃を掻き揚げて去 っていく。古錆びた停留所に立ち尽くした篠原珪一は、それを見送 ると、整った額にじんわりと浮かんでくる汗を拭って眩しげに目を 細めた。 強い日差しに照らされた大地が、白一面の強い光りの照り返しで目 に突き刺さる。更に湿気を含んだ夏特有の熱気は、むせ返るような 植物の濃厚な香りを含んで、五感を奪っていく。 何もかもが、苛立たしい。 「篠原―――」 唐突に呼ばれた名に、手にした荷物を取り落としそうになるのを、 ぎりぎりで堪えて振り返ると、背後に立っていたのは想像通り、 人の良さそうな笑みを浮かべた大男だった。ただ違ったのは、日 に焼けた肌の色ぐらいだろうか。 「相変わらず、すっげー田舎」 それだけ云うと、篠原は手にした大玉の西瓜を相手に投げつけた。 手を滑らせれば最後の代物を、大男――高橋要は器用に受け止め てみせる。 「こんなの お前、うちの冷蔵庫には入らんぞ?」 「なら、食うな」 「仕方ない… あとで裏の川に浸けておくか」 高橋は、ポンポンと宥めるようにニ、三度西瓜の背を叩くと、よ っこらせという掛け声と共に、右肩へと担ぎ上げて歩き始めた。 その背に、すかさず篠原の悪口が掛かる。 「じじくせー」 高橋は足を止めると、眉を顰めて振り返った。篠原は、以前から 決して真直ぐではない性格の男ではあったが、今日は一段と酷い 毒を含んできたらしい。 篠原は、いつも毒を含んでここに来る。 「機嫌悪いなぁ」 「暑いんだよ」 「なら来るなよ、こんな田舎」 明らかに本気でないとわかる口調で篠原をつきはねると、高橋は 再び家に向かって歩き始める。篠原は変わらず、けだるそうな様 子のまま、慌てるでもなく後に続く。 延々と続く、砂砂利の道。 やはり夏の日差しに当てられて、感覚が狂っているのだろうか。 あるいは時間の流れが。 道脇に伸び始めた茅が、葉擦れのざわめきを立てる。 そこでようやく、現実に風が吹いているのだと気づくのだ。 * * * 「お、電話だ」 安っぽい日本家屋の庭先をくぐった高橋は、高いベル音に気づくと そのまま家へと駆け出した。ばたばたと玄関口をかけあがると、西 瓜を置くのも忘れたまま、ダイヤル電話を抱え込んだ。 外に投げ出された靴を拾った篠原は、更に不機嫌そうな表情で開き っぱなしの戸口をくぐる。 「西瓜、どーすんだよ」 「だから後で川に浸けとくよ。そこの柿の木の横に、川に下りる梯 子があるだろ」 「どこに?」 「だからその…」 柿の木が判らず右往左往する様子に、高橋は呻き声をあげると、電 話の相手に此方からかけ直す旨を伝えて受話器を置く。 「家にはいってろ、藪蚊にかまれてもいいのか? お前の、その自慢の顔は、一応仕事モノだろうが」 「顔で勝負してるわけじゃねーんだよ、ちょっとくらい蚊に食われ たぐらいで、俺の舞台人気が落ちるもんか」 「あー、そーかね」 云い始めたら聞かないのだ、勝手にさせておくしかない。 藪蚊にかまれた痒さは、並の蚊以上だというセリフを飲みこんで、 高橋は柿の木の脇に立つ。 「これが柿の木」 「わかんねーよ」 答えを無視して細い梯子を下り始めた高橋は、後に続いて梯子に足 をかけた篠原を慌てて制す。こんなヤワな自作の梯子では、とても 男二人の体重は支えきれない。一旦川辺に足を付けてから、下りて 来ても構わないとの合図を送る。 「なんか、生ぬるい」 高橋の背後では、川辺に下りた篠原が、足元の水溜りに指を触れて 不平をもらしている。 「当たり前だ、そこは水の流れが止まってるだろ」 そう云って川の流れに手を入れながら、ひやりと冷たい個所を探し て手ごろな岩を見繕う。その岩に西瓜を被うネットを括り付ける様 子を、水面近くにしゃがみ込んだ篠原が興味深げに覗きこむ。 「この川な、今夜になったらホタルが出るぞ」 「え、うそ?」 「この時期、ここに来たことなかっただろ。 もうちょっと遅かったらアウトだったが、ぎりぎりな」 「ふーん…」 興味あるのかないのか判らない篠原の返答を聞きながら、家へ戻る 梯子に高橋は手をかけた。 「おい、戻るぞ…」 「なあ、死ぬってどんなカンジかな」 次の瞬間、派手な水飛沫をあげて篠原の上半身が水中に沈んだ。 篠原の背中に向かって、無言で高橋が蹴りを入れたのだ。 「……なにしやがるッ!!」 「背中に藪蚊が止まってた」 「嘘つけッ!!」 ぼたぼたと上半身から水を滴らせて、篠原が吼える。 「お前が、唐突にバカな質問をするからだ」 片手を伸ばして川から引き上げようと、高橋は篠原の腕を掴んだ。 しかし篠原は、それを無言で拒絶したまま動かない。 幾ら夏の日差しが強くとも、川の水は遥かに冷たい。自分がびしょ ぬれにしてしまった以上、このままほおって置く訳にもいかないの に。この頑固者を前に、どうしたものかと途方に暮れた高橋は、や がて篠原の顔に滴るものが、川面を被う水ばかりではないことに気 づいた。 「悲しいのか?」 「わからない」 「とにかく上がって着替えろよ、ほら」 再び腕に力を込めると、水の中から引きずり出した男を梯子の上に 追いやる。その背を見送りながら、高橋はため息をついた。 * * * 頬を過ぎる風の向きが変わった頃、水蘚臭いと不平を漏らしつつ、 着替えを終えた篠原が、ようやく縁側に顔を出した。高橋の横に座 って彼の手にした煙草を奪うと、不味いと更に不平を吐く。 「蚊遣りは?」 「さすがに、そこまではなー」 「黒電話のくせに」 「うるせー」 「そういえばさ、お前、今日仕事は?」 「あのなあ… 今日は土曜、一応学校休みだろ」 「小学校の教師なんか、全然見えねーから忘れてた」 奪われた煙草に代わって、高橋は二本目の煙草に火をつける。 煙草の煙などで一緒に吐き出せるものならば、さっさとその毒を吐 ききって欲しい。 「電話で聞いた。お前の劇団のヤツが死んだって…」 「……」 「死が重いのか」 「わからない、でも世界が終わった」 「世界?」 篠原は、深く煙を吐き出した。 「一つの物語が終わるだろう? そうすると、それまでそこに登場していた人間も、世界も、何も かもが消えて、この現実の世界には存在しないものに代わってし まう。それが…」 「それが、そいつの死か?」 物語が終わる。 これまで自分の存在していたはずの世界が終わり、新しい物語の中 で生きなければならない。 「冷えた、西瓜が食べたい」 「あのなあ…」 「それと、ホタル」 「ホタルは食えんぞ」 またもや年寄りくさい掛け声をあげて、高橋は腰を上げると、冷え た西瓜を取りに川辺へと向かった。 その背を見送る篠原が、小さく呟く。 「この世のわずらいからかろうじてのがれ、永の眠りにつき…」 |